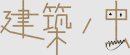|
|
011 セキスイハイムM1
|
|||
|
辻泰岳 Tsuji,Yasutaka
建築史家 1982年生まれ
東京大学大学院工学系研究科 建築学専攻博士課程修了 齋賀英二郎 Saiga,Eijiro
建築家 1983年生まれ
早稲田大学大学院理工学研究科 建築学専攻修士課程修了 八木香奈弥 Yagi,Kanami
建築家 1982年生まれ
東京大学大学院工学系研究科 建築学専攻修士課程修了
e-mail: info[a]archinsects.jp
|
富田玲子さんの話を伺っていると、いったい起こった物事に対して富田さんがとった態度が受け身なのかそうでないのか、ちょっと判別がつかない。 我々は2011年12月現在休業中のカフェ・スペースで、コーヒー片手に菓子をほおばりながら、長谷川町子世界の住人のような富田さんの話にいつの間にか耳を澄ませるばかりであった。彼女が腰かけていた椅子は剣持勇デザイン研究所の《椅子OM5008》(1965年)。量産を目的にして成型合板・ビニールレザー・鉄で作られた椅子を、丹下健三が気に入ったうえにちょっと注文を付け、その後いくつか展開したデザインのひとつだ。つぶれた碁会所で使われていたのを数点、捨てるのならばと貰い受けてブルーの生地に張り替えたのだという。工業化時代、建築家/デザイナーが見た夢の欠片が、起承転結を欠いたままアッセンブルされて洋館時代の家具と並置され、象の住処になっている姿を目の当たりにしているのだ。そう思い至ると、連想は一端停止せざるを得ない。 |
|||
|
|
||||